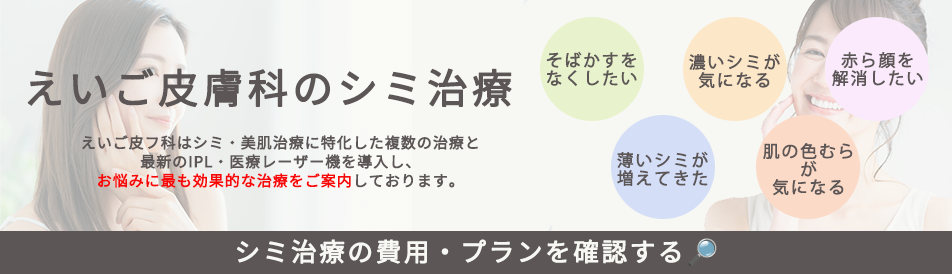皮膚科でシミ治療を行う場合に処方される飲み薬・塗り薬について解説!
2025/08/26
シミ治療を始めたい方に向けて、皮膚科で処方される飲み薬・塗り薬の効果や組み合わせ、治療費用までを皮膚科医の視点で分かりやすくまとめました。
自分に合った治療のヒントが見つかります。
Contents
1. 皮膚科で処方される飲み薬(内服薬の種類と効果)

シミ治療において、内服薬は体の内側からメラニンの生成を抑えるアプローチとして用いられます。
特に炎症やホルモンバランスが影響するシミに対しては、外用薬だけでなく内服薬の併用が検討されることもあります。
患者の体質や生活習慣に応じて、医師が適切な薬を選ぶことで、より効果的な治療が可能になります。
ここでは、実際に皮膚科で処方される代表的な内服薬と、その特徴について詳しく解説します。
1-1. トラネキサム酸(トランサミン)
炎症やメラニンの生成を抑えて、肝斑や色素沈着を改善する内服薬です。
効果:メラノサイトの活性化を防ぎ、シミのもととなるメラニンの過剰生成を抑えます。肝斑や炎症後の色素沈着に対して特に有効です。
副作用:まれに胃の不快感や食欲不振がみられることがあり、ごく一部の方では血栓症のリスクがあるため、医師の管理下での服用が必要です。
1-2. シナール(ビタミンC)
ビタミンCを補い、シミの原因となるメラニンの生成や酸化を防ぐ内服薬です。
効果:抗酸化作用により紫外線やストレスで増える活性酸素を抑え、メラニンの生成や沈着を防ぎます。肌の明るさを保つサポートにもなります。
副作用:基本的には安全性が高い薬ですが、大量に摂取すると下痢や腹痛を起こすことがあります。
1-3. L-システイン(ハイチオールなど)
アミノ酸の一種で、肌の代謝を助けながらメラニンの排出を促す内服薬です。
効果:肌のターンオーバーを促進して、シミの原因であるメラニンを体の外へ排出しやすくします。抗酸化作用もあり、シナール(ビタミンC)との併用で相乗効果が期待されます。
副作用:まれに吐き気や胃の不快感などの消化器症状が出ることがあります。
1-4. ユベラ(ビタミンE)
ビタミンEを補い、血行促進や抗酸化作用によって肌の健康を守る内服薬です。
効果:体内の酸化を防ぎ、メラニンの生成を間接的に抑えるほか、血行を促して肌の代謝を整えます。乾燥しがちな肌のうるおい維持にも役立ちます。
副作用:重い副作用は少ないとされていますが、まれに吐き気や頭痛などの症状があらわれることがあります。
1-5. 内服薬のメリット・デメリット
内服薬は、塗り薬では届きにくい体の内側からシミに働きかける方法として活用されますが、効果を十分に引き出すためには特徴を理解した上で使うことが大切です。
メリット
- 手軽に続けやすい:飲み薬は塗り薬と違い、時間や場所を選ばず服用できるため、忙しい方でも継続しやすいのが特長です。
- 全身に作用する:内側から作用するため、顔だけでなく体の他の部位にできるシミにも効果が期待できます。
- シミの予防にも有効:継続することで、メラニンの生成を抑え、シミの再発や新たなシミの予防にもつながります。
デメリット
- 即効性がない:効果を実感するまでには一定の期間がかかるため、数週間〜数ヶ月の継続が必要です。
- 副作用の可能性がある:まれに胃の不快感や吐き気などの副作用が生じることがあります。特に持病がある方や他の薬を服用している方は、医師の判断が重要です。
- 単独での効果は限定的:内服薬だけでは効果が十分でない場合があり、外用薬や施術と併用することでより高い効果が得られることもあります。
2. 皮膚科で処方される塗り薬(外服薬の種類と効果)

外服薬は、シミができた部分に直接塗布することで、メラニンの排出や生成の抑制を狙う治療方法です。
肌質やシミの状態に応じて、効果と安全性のバランスを考慮しながら処方されるのが一般的です。
主に使われる薬には、美白成分として知られるハイドロキノンや、肌のターンオーバーを促すトレチノインなどがあり、それぞれ異なる作用を持っています。
2-1. ハイドロキノン
メラニンの生成を抑えてシミを薄くする、美白効果の高い外用薬です。
効果:チロシナーゼという酵素の働きを阻害し、シミの原因となるメラニンの合成を抑制します。濃いシミや色素沈着に対して特に効果が期待されます。
副作用:赤み・かゆみ・乾燥などの刺激症状が出ることがあり、肌への負担が強いため、使用濃度や頻度には注意が必要です。
2-2. トレチノイン
肌のターンオーバーを促進し、シミの原因となる古い角質を排出する外用薬です。
効果:皮膚の代謝を早めてメラニンを含む角質を排出し、ハイドロキノンとの併用でより高い美白効果が期待されます。小ジワやくすみにも有効です。
副作用:皮むけや赤み、ヒリつきが出やすく、紫外線に敏感になるため、治療中は日焼け止めが必須です。初期反応が強いこともあるため、医師の管理下での使用が推奨されます。
えいご皮フ科では、肌のターンオーバーを促進して毛穴詰まりやくすみ、小ジワに働きかける「トレチノイン配合GEL」と、肝斑や炎症性ニキビ、色素沈着に対して低刺激で安全性の高いケアが可能な「メトメランクリーム」の2種類を処方し、幅広い肌質や症状に対応しています。
患者様の肌に合った治療を提供いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
トレチノイン配合GELとは

トレチノイン配合GELは、ビタミンA(オールトランスレチノイン酸)を高濃度で含む医療機関専用の外用薬です。
市販のレチノール製品よりも強力に肌のターンオーバーを促進し、ニキビやシワ、毛穴の開きなど、さまざまな肌悩みに幅広く対応します。
えいご皮フ科では、医療機関でのみ扱える高濃度のトレチノインを独自に配合した「Acne mix」「Consensus mix」を使用し、患者様一人ひとりに合わせたケアを提供しています。
トレチノイン配合GEL(Acne mix)を使用した症例
お悩み:毛穴の開き・赤み

トレチノイン配合GEL(Consensus mix)を使用した症例
お悩み:毛穴の開き・ニキビ

画像:https://hifuka-eigo.com/beauty/tretinoin/
| 特徴 | 内容 |
| 有効成分 | トレチノイン(高濃度ビタミンA誘導体) |
| 対応できるお悩み | ニキビ・ニキビ跡、くすみ、毛穴の開き、小じわ、肝斑、皮脂づまりなど |
| 主な作用 | ターンオーバー促進、皮脂分泌抑制、コラーゲン生成促進、ヒアルロン酸産生促進 |
| 使用に向いている方 | 従来のニキビ治療で満足できなかった方、小じわや毛穴が気になる方、ハリ感を求める方 |
| 従来薬との違い | レチノール製品に比べて作用が強く、医師の指導下で安全に高い効果が得られる |
| 注意点(禁忌) | 妊娠中・授乳中、重度の皮膚炎、感染症部位、日焼け直後、過去の過敏症などがある方は使用不可 |
トレチノイン配合GELは、肌の代謝を根本からサポートする力があり、ニキビや小じわ、毛穴などさまざまな肌悩みに対応できる可能性がある治療法として医療機関で活用されています。
ただし、強い反応が出ることもあるため、使用にあたっては必ず医師の管理のもとで進めることが重要です。
トレチノイン配合GELについて、詳しくはこちらをご覧ください。
▶︎トレチノイン配合GEL(Acne mix/Consensus mix)|えいご皮フ科
メトメランクリームとは

美白・抗炎症作用を持つ特定の成分を独自に配合したクリームです。
肝斑や色素沈着、ニキビによる赤みやくすみなど、さまざまな肌トラブルに対応できるのが特長です。
低刺激で肌への負担が少ないため、敏感肌や刺激に弱い方にも使いやすい選択肢とされています。
メトメランクリームを使用した症例
お悩み:肝斑

| 特徴 | 内容 |
| 対応できるお悩み | 肝斑、ニキビ・ニキビ跡、くすみ、毛穴の開き、炎症後の色素沈着 |
| 主な作用 | メラニンの生成抑制、抗炎症、低刺激で安全性が高い |
| 使用に向いている方 | 肌が赤くなりやすい方、従来のニキビ治療で効果が出なかった方、肝斑治療で刺激を避けたい方 |
| 従来薬との違い | トレチノインやハイドロキノンに比べて副作用が少なく、穏やかな治療が可能 |
| 注意点(禁忌) | 妊娠中・授乳中、重度の皮膚炎、感染症部位、日焼け直後、メトホルミン過敏症の既往がある方など |
メトメランクリームは、刺激を避けながらも効果的な肝斑治療を求める方にとって、注目される新しい治療選択肢です。
使用の可否や最適な使い方については、医師の診察に基づいて判断されます。
メトメランクリームについて、詳しくはこちらをご覧ください。
▶︎メトメランクリーム|えいご皮フ科
2-3. 外服薬のメリット・デメリット
塗り薬は、シミのある部位に直接作用するため、治療効果を実感しやすい反面、使用方法や肌質によって注意が必要な点もあります。
メリット
- 局所的にアプローチできる:シミのある場所にピンポイントで使えるため、効率的にメラニンに作用します。
- 比較的早く効果を実感しやすい:個人差はありますが、数週間で肌の明るさやトーンの変化を感じることがあります。
- 組み合わせ治療に向いている:内服薬や施術と組み合わせることで、より高い相乗効果が期待できます。
デメリット
- 副反応が出やすい:ハイドロキノンやトレチノインは効果が高い分、赤み・かゆみ・皮むけといった副反応が出ることがあります。
- 紫外線対策が必須:治療中の肌は刺激に敏感なため、日中は必ず日焼け止めを使用する必要があります。
- 継続使用と医師の管理が必要:効果を出すためには正しい使い方を守ることが大切で、自己判断での使用はトラブルの原因になります。
3. 市販薬と皮膚科でもらえる医薬品との違い

シミ治療を考える際、市販薬と皮膚科で処方される医薬品のどちらを選ぶべきか迷う方も多いかと思います。
市販薬は手軽に入手できる反面、成分の濃度や効果に違いがあり、医薬品ほどの効果が得られにくいこともあります。
3-1. 市販薬と医薬品のメリット・デメリット
ここでは、それぞれの特徴を理解し、ご自身に合った治療方法を選ぶための参考として、市販薬と処方薬のメリット・デメリットを表にまとめました。
| 区分 | メリット | デメリット |
| 市販薬 | ・処方箋なしで手軽に購入できる
・比較的安価で始めやすい ・軽度のシミや予防目的で使いやすい |
・有効成分の濃度が低く、効果が出るまでに時間がかかる
・配合成分が限定的で、強力な成分は使えない ・自己判断による使用で肌トラブルのリスクがある |
| 皮膚科の医薬品 | ・医師の診断に基づく処方で効果が出やすい
・高濃度の成分や医療用成分を使用可能 ・内服薬や施術との併用など多角的な治療が受けられる |
・診察と処方のため通院が必要
・自由診療となるケースが多く、費用負担が大きくなる可能性がある |
それぞれに利点と注意点があるため、シミの種類や症状の強さ、ライフスタイルに合わせて選択することが大切です。
悩んだ際には、皮膚科での診察を受けることで、より効果的な治療方針を見つけやすくなります。
4. 【シミの種類別】処方される薬の組み合わせ

シミと一口に言っても、その種類によって原因や適した治療法は異なります。
医療機関では、シミのタイプを正確に見極めたうえで、それぞれに合った内服薬と外用薬の組み合わせが提案されます。
下記の表は、代表的なシミに対して処方される薬の例をまとめたものです。
ご自身のシミのタイプを把握し、適切な治療を検討する際の参考にしてください。

シミの種類によっては、症状が複合していたり、見た目では判断しにくいケースもあります。
正確な診断をもとに、肌質や生活習慣に合った薬を選ぶことが、治療効果を高めるポイントです。
4-1. 薬だけでは効果が期待しにくいシミにはレーザー治療等も検討する
一部のシミは、薬による治療だけでは十分な効果が得られないことがあります。
特に、色が濃く長年定着している老人性色素斑や、真皮にまでメラニンが沈着しているタイプでは、内服薬・外用薬の単独使用では改善が難しいこともあります。
こうした場合には、レーザー治療やフォトフェイシャルなど、光や熱を用いたアプローチが検討されます。
薬との併用により相乗効果が期待できるため、症状に応じて柔軟な治療選択が重要です。
気になるシミがなかなか改善しないと感じたら、専門医による相談をおすすめします。
5. シミ治療の費用について

シミ治療は使用する薬や治療法によって費用が大きく異なります。
基本的に美容目的とされる治療は保険の対象外であり、自由診療として扱われるケースがほとんどです。
ここでは、シミ治療にかかる費用の基本的な考え方と、保険適用になる可能性について解説します。
5-1. シミ治療は原則「自由診療」
一般的に、シミ治療は「美容医療」に分類されるため、健康保険は適用されず、すべて自己負担となる自由診療です。
たとえば、トレチノインやハイドロキノンなどの外用薬、レーザーやフォトフェイシャルなどの治療もすべて自由診療に該当します。
料金は医療機関ごとに異なり、使用する薬の種類や濃度、治療内容によっても変動します。
診察の上で見積もりを提示されることが多いため、事前に確認しておくと安心です。
5-1-1. 保険適用になるケースはある?
一部のシミに類似した皮膚疾患、たとえば炎症性色素沈着やアトピー性皮膚炎による色素沈着が原因で治療が必要と判断された場合は、保険診療の対象になることがあります。
また、明確な外傷ややけどの跡など、医学的に治療の必要があると診断されたケースでも保険が適用される可能性があります。
ただし、あくまでも「病気」として扱われるかどうかが基準となるため、美容目的の色素沈着改善では保険の適用は難しいのが現状です。
詳細は診察時に医師に確認することをおすすめします。
5-2. 自由診療でのシミ治療の費用相場
自由診療では、治療法や薬の種類によって費用が異なります。
以下に、代表的なシミ治療の費用相場を一覧でご紹介します。
使用する薬剤の濃度や治療の回数によって変動するため、あくまで目安として参考にしてください。
| 治療内容 | 費用相場
(1回または1ヶ月あたり) |
説明 |
| 内服薬 (トラネキサム酸・ビタミンCなど) |
約1,500円〜3,000円程度 | 月単位で処方されるケースが多く、予防的な使用にも向いています。 |
| 外用薬 (ハイドロキノン・トレチノインなど) |
約2,000円〜5,000円程度 | 濃度や処方量により価格は変動。複数種類の併用で相乗効果が期待されます。 |
| メトメランクリーム | 約7,000円〜10,000円程度 | 低刺激で安全性の高い複合クリーム。肝斑や色素沈着に使用されます。 |
| レーザー治療 (スポット・全顔) |
約5,000円〜30,000円程度 | シミの範囲や種類によって異なり、複数回の照射が必要な場合もあります。 |
自由診療では、治療の選択肢が幅広く、自分に合った方法を選びやすい反面、費用の差が大きいため、初回カウンセリングなどでしっかりと料金体系を確認しておくことが重要です。
複数の治療を組み合わせる場合は、セット価格や定期プランが用意されていることもあります。
5-3. シミ治療の費用を抑える方法はある?
自由診療で行うシミ治療は、治療内容によって費用がかさむことがありますが、いくつかの工夫でコストを抑えることも可能です。
治療の継続を考えている方は、以下のような選択肢を意識することで、負担を減らしながら効果的な治療を続けやすくなります。
お得なプランを利用する
多くのクリニックでは、定期コースやセット割引などの割安プランが用意されています。
たとえば、内服薬と外用薬を一定期間まとめて処方する「○ヶ月コース」や、レーザー照射を複数回受けるセットプランなどを選ぶことで、1回あたりの費用を抑えることができます。
通院頻度や治療期間が明確な方には、こうしたコースの活用が特におすすめです。
ジェネリック医薬品を選ぶ
薬の費用を抑えたい場合には、ジェネリック医薬品を選ぶという方法もあります。
成分や効果は先発薬と同等でありながら、価格が比較的安く設定されているため、継続的な治療を考えている方にとって経済的な選択肢になります。
ただし、薬の種類によってはジェネリックの取り扱いがない場合もあるため、診察時に医師へ相談してみましょう。
費用を抑える工夫をすることは大切ですが、自己判断で薬を選んだり、必要以上に安さを重視すると、肌に合わない治療を選んでしまうリスクもあります。
無理のない範囲で続けられる治療方法を、医師と一緒に見つけていくことが安心・安全な選択につながります。
6. 皮膚科でのシミ治療の流れ

シミ治療は、ただ薬を処方するだけでなく、肌の状態を総合的に把握し、一人ひとりに合った方法を選ぶプロセスが重要です。
ここでは、実際に皮膚科で行われるシミ治療の流れについて、初回の来院から治療開始までのステップを具体的にご紹介します。
6-1. カウンセリング
- 肌悩みや生活習慣のヒアリング
- 過去の治療歴やスキンケア習慣の確認
まずは、現在の肌悩みや生活習慣、過去の治療歴などを問診票に記入し、医師またはスタッフが丁寧にヒアリングを行います。
日常のスキンケア方法や日焼けの状況なども確認されるため、できるだけ正確に伝えることが、適切な治療提案につながります。
6-2. 診察
- 医師による視診
- 肌診断機を使用した詳細な測定(隠れジミ・水分量・皮脂量など)
- 治療計画の説明と薬・施術の提案
カウンセリングの内容をもとに、医師が肌の状態を詳しく診察します。
ここで大きな役割を果たすのが、肌診断機の存在です。専用の肌診断機を用いることで、目視ではわかりにくい隠れジミや肌の水分量・皮脂量・キメの乱れまで数値化でき、より精密な診断が可能になります。
当院では、奈良院・京都院・尼崎院の3院に最新の肌診断機re-Beau2(レビュー2)を導入しています。
re-Beau2(レビュー2)は、肌内部のメラニン量や色素の分布、深さを高精度で可視化できる専用機器で、シミや肝斑、そばかすなどの診断に活用されています。
目に見えない初期のシミや、肉眼では判断しづらい真皮性の色素沈着も確認できるため、治療前に肌状態を正確に把握し、より適切な治療方針を立てることが可能です。
診断の後に医師から治療方針の提案を行い、外用薬・内服薬・レーザー治療など、選択肢の中から肌状態やご希望に沿った方法を案内します。
費用や治療期間についてもこのタイミングで詳しく説明されるのが一般的です。
6-3. 治療開始
- 外用薬・内服薬の処方または施術の予約
- 必要に応じて通院・再診で経過を確認
治療方針に同意いただいた後、実際の治療がスタートします。
内服薬・外用薬によるケアであれば当日から使用が可能で、レーザーや光治療などを希望する場合は、後日の予約を行うケースもあります。
治療後は肌の変化を確認するため、一定期間ごとに再診を行い、必要に応じて治療内容の見直しが行われます。
こうした丁寧なプロセスを通して、肌への負担を抑えつつ、より効果的なシミ治療を目指すことができます。
治療に不安がある方は、まず肌診断だけでも受けてみると、自分の肌の状態を客観的に知るよい機会になります。
7. まとめ

シミ治療は、単に美白を目指すだけでなく、肌全体のコンディションを整え、年齢や生活環境による変化に前向きに向き合うための大切なステップです。
内服薬や外用薬にはそれぞれ特徴があり、シミの種類や肌の状態に応じて適切に組み合わせることで、治療効果を高めることができます。
また、市販薬と医薬品の違いを理解することで、ご自身の悩みに本当に合った治療を選択できるようになります。
費用面でも、自由診療の相場や保険が適用されるケース、費用を抑える方法を知っておくことで、無理のない治療継続につながるでしょう。
さらに、肌診断機の活用によって、目に見えない肌内部の状態を把握し、将来的な肌トラブルにも先回りした対策が可能です。
シミに悩んでいる方は、まず信頼できる医師のもとで肌の状態を丁寧に確認し、自分に合った治療法を見つけてみてください。
正しい知識と適切なケアが、透明感のある健やかな肌への第一歩になります。